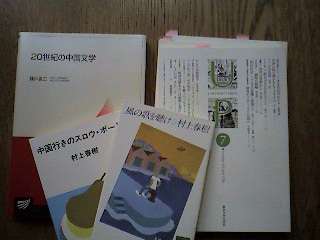『1Q84』による、この世界への意味の付与 [村上春樹]
結論から言って、自分はこの物語を承認する。肯定する。
この物語は、村上春樹がこの世界を意味づけたものであると思う。
読み終わって、直後に思ったのは、主人公たちはもとの1984年に帰還することができたが、われわれはどうなのだろう、ということだった。結局われわれは、サリン事件の後の世界、あるいは9.11の後の世界、すなわち何でも有りのこの世界に引き続き生きているのであり、彼らのようにもとの世界に戻るすべを知らないし、ここで生き続けるしかない。
しかし、物語において、1Q84年はただ遺棄されたのではなかった。主人公たちは、1Q84年にも彼らなりの意味を付与したのである。1Q84年は単に論理が危険なほど通用しない世界というだけではなく、そこは彼らが必然的にそこを通過したがゆえに、それまで熱望していたものを手に入れることができた、そういう世界でもあった。1Q84年でしか彼らは自分たちの欲してきたものを得られなかったのだという意味、価値が付与されているのである。そこに、1Q84年にいまだ生き続けるわれわれにも、希望が与えられているのではないだろうかと思う。
それでは、主人公たちが欲した、そのものとは何か。それは自分たちの再会である。1984年とは位相を異にしてしまった1Q84年という世界において、それが異空間であることを唯一示す「二つの月」。しかし二人の他にその指標は誰の目にも見えない。他の人間たちにとって、1Q84年は変わらず1984年のままなのであろうか。それが二人には分からない。とにかく、二人にとって、それはすでに変化してしまった1Q84年なのである。彼らはそれぞれに、この世界が1Q84年という〈異〉なる世界であり、危険な世界であって、そこから逃れなければならないと知っている。そうした二人が邂逅しえた、ということが重要な意味を示しているのだと思う。
以下、以前ここに書いたことなどにからめて、思ったことを散発的に書き出してみる。
① 村上作品初とも言える女性の主人公
村上作品における本書の位置づけとして、もっとも顕著と言える特徴の一つは、女性を主人公の一人にして、彼女の登場場面においては女性の視点で語っている点だと思う。もう一人の男性主人公については、これまでの村上作品に登場してくる男性と雰囲気はそれとなく似ていたりもするが、大きな変化は、その人物(男性)を内面から描くのではなく、外側から描いていることだと思う。しかも、この二人の主人公の中では青豆(女性)の方が天吾(男性)より状況をよく把握しているし、むしろ天吾は導かれるままというか、いまいち自分の置かれた状況をよく分かっていない。したがって、読者としては、どちらかと言うと女性の側に立って物語をハラハラしながら読むということになる。ちなみに、物語の中では彼ら自身もそのことを知っていて、最終局面において天吾は青豆に、自分が状況を知らなさすぎるのはフェアじゃない、と訴えている。
② 三人称という表現スタイル
以前に書いたが、村上春樹はあるインタビューで、若者を描くにあたりウソをつきたくないから三人称で書くように変わって来たと語っていた。それを念頭に置けば、女性を主人公の一人とした本作品が三人称形式で書かれたことは必然だったのだろう。さらに、そうした三人称のスタイルを強調するような表現として、なんと作者目線が出てくる箇所が三カ所あり、これには「これが村上作品なのか!?」という感慨があった。339頁と455頁では、登場人物たちがニアミスする場面で、作者の目が登場し、「もしこうであれば、こうなった」と状況を明確に説明するのである。また、566頁では、「リトル・ピープル」の顔を説明するにあたり、「あなたや私とだいたい同じ顔をしている」と、作者と読者を引き合いに出しているのである。これは、これまでの村上作品ではありえなかった手法で、正直けっこう驚いた。アクロバティックな説明手法というか、一見、素人っぽい語り口になりそうな所なので、実験的というか、新鮮な印象を受けた。
③ 小説・物語・書物の可能性
この作品の中にはもう一つの作品が登場する。主人公の一人、天吾は小説家の卵である。その彼が関わって発表された小説を中心にして物語が展開していくのであり、物語の入れ子構造となっている。その物語内物語の非常に重要な位置づけから、世界における物語のもつ重要性というものを感じた。小説という題材を使いながら、非常にリアルな世界を描いたと思う。それは、すなわち、小説・物語・書物のもつ可能性を示した、というふうにも取りたい。
④ 村上は老年を描けるかという問題
本作品には、老若男女が登場する。主人公は三十歳の男女ではあるが、だからと言って彼らだけを描くのではない。そこには、天吾の死にゆく父がおり、青豆に関係する七十代の「老婦人」がいる。物語の中では、彼らの人生をも丁寧に、いくつかの視点から、重層的に描かれる。したがって、以前このブログでは、村上春樹はなぜ若者ばかりを書いて中年や老年を描かないのかという疑問を記したが、村上は決して中年や老年を書けないわけではなかったのだ。その点は、ここできちんと訂正しておきたい。
⑤ 作品で宗教を描くということ
この物語における宗教の位置については、なかなか難しいなあという所である。
BOOK 3 まで読んでみて、ひとまず思うのは、やっぱり、一方では、結局この作品において宗教は、ファンタジーの源泉という位置づけ以上の意味はないのではないかとことである。つまり、物語におけるファンタジーの出どころとしては、特に宗教でなくても良かったのかもしれないし、この作品において宗教はあくまで背景にしか過ぎないのではないかとも思う。
しかしまた一方で、物語の中でいくつかの死を扱う上で、やはり作者が宗教を欠かせないと考えたのではないか、少なくとも宗教を扱うのが自然だ、ふさわしいと考えたのではないかとも思う。しかし、ここでいう意味における宗教は、カルト教団の中に登場するのではなく、むしろカルト教団の外部において、青豆やタマルの中に、カルト的に何かを信奉するのでははい、懐疑をも含んだ現代的な敬虔さという形をとって登場するように思った。
とはいえ、カルト教団から出てくるファンタジーについては、「リトル・ピープル」を筆頭に、いまだ謎が多いし、カルト教団的なる〈宗教〉についても、ファンタジーの豊かな源泉として、この物語においてはもちろん非常に重要な存在であるとは言える。
以上のように、数々の不思議な問いを含み込みながらも、最後は物語を予測のつかない形で見事に収束させ、世界に肯定を与えた本作品によって、おそらく村上春樹は小説家として数段高いステージに上がったと思う。いくつもの問題が雑多に混淆し展開するこの長編小説は、村上春樹いうところの総合小説の、少なくとも一端を示してくれた。『1Q84』は、同時代に読むにふさわしい物語であった。
『1Q84』BOOK 3 を読み始めた [村上春樹]
朝7時のNHKニュースは、この3巻目の刊行をトップ・ニュースで扱った。
そんなこと、前代未聞ではなかろうか。
テレビからは、開店時間を早めて販売する東京・神保町の三省堂の様子や、人々が出勤前に列を作って購入する風景が生中継で映し出された。書籍取次最大手のトーハンを取材したVTRでは、『1Q84』BOOK 3 が、公式発売前の流通過程で内容がさらされないよう、通常ありえない箱詰めで出荷されていく場面が流された。
そこまでやるか、新潮社。まさか、派手ぎらいの村上春樹自身が、こうした販売手法を自ら希望するはずはない、と思うのだが。
そして当日夜、うちにも、ネット書店で予約していた本書が届いた。
目次を見て、本文を1行読んで、ことの次第が飲み込めた。これはただものではない。ダン・ブラウンばり、ページターナーの予感が……。これってほとんどミステリーじゃないか。派手な販売手法も、まったく理由がないというわけではないのかもしれない、と思ってみた。
半分ほど読み進んだ現在、今のところ、大きな破綻はない。さて、この先どうなっていくのだろうか。早く決着をつけたいような、つけたくないような、微妙な心境の今日この瞬間。結末で破綻という事態だけは避けてくれ、と願う気持ちです。
電子書籍と村上春樹 [村上春樹]
しかし、思うのだが、これまで本作りや販売に携わって来た人間たちが、自ら電子書籍の脅威を語るというのには、何か違うものを感じる。自分としては、書物を読む、という行為は今後も変わらないと思ったりする。業界の経営陣やオピニオン・リーダーたちには、書物という形や、読むという人間の行為の意義をもっと語ってもらいたいと思う。簡単に言ってしまえば、もっと本に自信を持つべきではないか、ということだ。
もちろん、個人的に一ユーザーとしては、最新機器への興味もあるし、できれば早く電子書籍リーダーを使ってみたいとは思う。読みたい時にすぐにダウンロードして読めたらいいだろうし、一台の中に沢山の本を入れられれば、気分によって、読む本を選べる。それはスゴい便利だろう。でも、いざ購入する時に考えてしまうだろうと思うのが、バッテリーの問題と、通信料の問題だ。紙の本はかさばるかもしれないけれど、充電など必要なく、とってもシンプルな存在である。また、通信料に安くても月数百円かかるとすれば、それで文庫本くらい買えてしまう。
そんなこんなで、旋風吹き荒れるが、おそらく本のすべてが電子書籍に乗っ取られるわけではないと思う。だって、そうなったら、つまらないと思う。
ところで、この1月、有力書店によって構成される「書店新風会」が40年前から行なっているという「新風賞」という賞の発表があり、今回は『1Q84』を出版した新潮社と著者の村上春樹が受賞した、というニュースを先日『週刊読書人』で読んだ。この賞は「時代の思想・潮流を先覚し、また、活発な出版活動によって読者に大きな感銘を与え、書店売場の活性化に貢献した作品」を刊行した出版社と著者に授与される、という。
1月8日の贈賞式で代読された、村上春樹の受賞挨拶の中に、わが意を得たりと思うフレーズがあったので抜粋したい。
書籍をめぐる状況は、昨今大きく変わりつつありますし、この変化の多くは一見して書籍にたずさわる者にとって、あまり喜ばしいものではないように見えます。以前の時代とは違って、私たちは実に多様な新しいメディアと競合していかなくてはなりません。一種の情報の産業革命の真っ只中に私たちは置かれているように見えます。そこには思いもよらぬ価値の組み換えがあり、地盤の変化があります。しかし、何がどのように変化しようと、この世界には書物という形でしか伝えられることの敵わない思いや情報が変わることなくあります。活字になった物語という形でしか表わすことの出来ない魂の大きな震えが変わることなくあります。僕はそのことを信じて、この30年間、小説を書き続けてきました。(『週刊読書人』2010年1月22日号)
ちなみに、『走ることについて語るときに僕の語ること』(文藝春秋、2007年)では、ジョギング中にアメリカではほとんどの人がiPodで音楽を聴いているけれど、自分はMDプレーヤーを使用しているというくだりがある。音楽というものとコンピュータとをつなげたくない、とたしか書いていたと思う。上の引用は、この音楽の感覚とも似た話なのかもしれない。とはいえ、アメリカのアマゾンでは、もちろん、村上作品のキンドル・バージョンがふつうに売られているのではあるが。
グレイス・ペイリー『人生のちょっとした煩い』 [村上春樹]
あるいは、幸せと言うより、充実を感じる時、と言った方が、ピッタリかもしれない。
つい2、3日前に気づいたことだけれど、自分がそういう充実感を感じている時というのは、読みたい本がたくさんあるという時かもしれない。つまり、読みたい本がたくさんあって、それらを同時並行的に、時間を見つけて少しずつ読んでいる時期っていうことだ。
言い換えると、もっと時間があれば、一気に読み終えて、もっとさらに関連の本をたくさん読んでいけるのに、と歯がゆいほどに感じる時は、けっこう自分としては充実しているのかもしれない。
しかし、まれに「読みたい本がない」という精神状態に、何の理由もなく、ストンと落ち込んでしまうような時もあって、これは困る。もちろん、いつもほんの2日くらいで収まるので、ご心配には及びませんが、けっこうな脱力状態である。
数週間前も、そこにストンと落ち込み、低空飛行をしていたが、「ダメもとだ」くらいの気持ちで、自分の本棚を眺めてみた。そして、ふと手にしてみたのが、グレイス・ペイリーの短編集『人生のちょっとした煩い』(2005年、文藝春秋)である。どうしてこれが本棚にあるのかというと、村上春樹の翻訳書だからである。
脱力状態にて本書を手にしてみると、なにか妙にストレートに伝わるものがある。
村上春樹の訳者あとがきによると、著者ペイリーは、ロシアから移民してきたユダヤ人を両親として、1922年にニューヨーク市に生まれ、ロシア語とイディッシュ語と英語が同じくらいの割合で話されていた地域で育った、ということである。また、小説を書くかたわら、公民権運動家、反戦運動家、フェミニスト、環境保護運動家として先頭に立って活躍したということで、小説以外の仕事が多くて、作品の数は少ない。
本書に載せられた作品は、どれ一つとして同じ感じはなく、どれも違ったお話である。しかし、何というか、そこにはマイノリティーの視点があるのだと思う。移民2世のユダヤ人で、英語が得意でなく、かつ女性である、ということが、「アメリカ人作家」という枠を取り外した親近感を感じさせるのかもしれない。
村上春樹は、文体として、ペイリーとレイモンド・カーヴァーとの類似性を述べているのであるけれど、一般読者にはもっと自由な発想が許されていいだろう。ここでは、むしろ作品に描かれる日常性にこそ、両者の類似性を見たいと思う。カーヴァーは、アメリカの労働者階級のオジサンの日常について書いた。ペイリーは同様にオバサンについて書いたのだ。
特にペイリーの描く風景について、印象に残ったものの一つに、キリスト教社会であるアメリカの地で、ユダヤ人すなわちユダヤ教徒として感じる日常的な違和感があげられる。言わずもがな、ユダヤ教は旧約聖書の世界であり、新約のイエスをキリストとして認めないので、クリスマスを祝うことはしない。しかし、どうしても我が子はアメリカの学校行事の中で、クリスマス・ペイジェントを演じたりするわけだ。その是非を夫婦で議論したりする風景、それが妙に共感させられた。日本で言うなら、さしずめ、公立学校における日の丸・君が代問題ということになるのかもしれない。
収録作品はそれぞれ特徴的ですので、オススメです。
村上春樹のインタビュー [村上春樹]
この70ページにわたるロング・インタビューに、村上は非常に真摯に答えているようにみえる。そしてここに、ある回答が与えられているように思ったので、メモしておきたい。
ここで村上は、自分は総合小説というものを書きたいのだ、と語っている。村上の考える総合小説とは「とにかく長いこと、とにかく重いこと」「そしていろんな人物が、特異な人から普通の人まで次々に登場してきて、いろんな異なったパースペクティブが有機的に重ね合わされていく小説であること」だと言う。
「いろんな話が出てきて、絡み合い一つになって、そこにある種の猥雑さがあり、おかしさがあり、シリアスさがあり、ひとつには括れないカオス的状況があり、同時にまた背骨をなす世界観がある。そんないろんな相反するファクターが詰まっている。るつぼみたいなものが、ぼくの考える総合小説なんですよ。だからもうすぐ、ぼくも六十を過ぎるわけだけど、ドストエフスキーとまではいかないにしても、ぼくなりのそういう総合小説を徐々にこしらえていきたいと思っているんです。」
「ぼくにとっての総合小説というのは、たとえば、ティム・オブライエンの『ニュークリア・エイジ』がそういうものですね。あの小説のばらけ方と、ばらけることによって出てくる広がり。それからテーマがやたらと大きいことね。総合小説っていうのは、細部の出来よりは、全体のモーメントがものを言います。とにかくテーマがでかくないと面白くないですね。」
いま書いている新作(『1Q84』のこと)はその総合小説なのか、という質問に対しては、「ある意味ではそれに近いものになりつつあるのではないかと思います」と答えている。
なるほど、そうか。春樹は『1Q84』で「総合小説」にチャレンジしていたのか。たしかに『1Q84』の持っている世界というのは、ここで言われている総合小説の特徴を備えていると思う。つまり、春樹はけっこう健闘し、そうした試みもある程度かたちになっている、と言っていい。ティム・オブライエンの『ニュークリア・エイジ』(村上春樹訳、文春文庫)という例を出されると、たいへん分かりやすい。アメリカの学生運動時代の話で、大学におけるベトナム戦争反対運動に始まって、細部は忘れたけれど、とにかく物語がどんどんスゴい展開になっていく分厚いものだった。この本の訳者あとがきで、春樹は「総合小説」について書いていた。
またインタビューでは、こうしたでかい話を書くには、当然、一人称ではとても書ききれない、だから長期的に見れば自分の小説は一人称から三人称にシフトしてきた、というように、総合小説へ向けた方法論についても述べているのである。
「おそらく「蜂蜜パイ」(『神の子どもたちはみな踊る』収録)のような小説は、昔のぼくだったら、それこそ一人称で書いているでしょうね。そういうふうに書かなくなってきたのは、ぼくがそれだけ年を取って、たぶんもうこういう考え方はしない、たぶんもうこういう物の見方はしない、というところが出てきたからかもしれないですね。それが自分の中で嘘になっちゃわないように、一人称で書かなくなったという部分もあると思います。」
『1Q84』の主人公は三十歳前後の男女であり、語り口は三人称である。前回、「春樹はなぜいつも若者ばかりを主人公にするのか」という疑問形の批判を書いたが、そうではなく、実は、ずっと若者を主人公にしてはいても、一人称から三人称へという変化を遂げてきている、ということだったのだ。そうした、小説家として一貫した成長への方向性を持っているという点、そういう方向性を読者にも語ってくれるという点は、春樹のエッセイなんかを読んでいて一番おもしろいところだし、評価したいと思う。
少し脱線になるが、この引用の中でもう一つ目を引くのは、「自分の中で嘘になっちゃわないように、一人称で書かなくなった」という点だ。春樹はつねづね、小説家は嘘をつくのが仕事、と語ってきたし、今年2月のエルサレム賞受賞の記念講演でもそのように枕を置いた。しかし講演では続けて「でも、きょう、うそをつくつもりはありません。真実をお話ししましょう」と言って、ガザ地区における戦闘について言及したのであった(毎日新聞、2009年3月2日)。こういう、ウソとホントというところの考え方も興味深い。が、また別の話としておく。
現在、3巻目を執筆中ということであるから、もしかして、この『1Q84』が総合小説として結実する、ということを期待できるかもしれない。まだまだ途上なのだ。『1Q84』も、村上春樹も。
『1Q84』を読み終えた [村上春樹]
読後抱いたのは、思い切って一言でいってしまうと、失望感であった。
自らを振り返ってみて、読了直後の自分の感想が、その後もずっと変わらないなどということはない。村上作品をとってみると、たとえば高校生の時に『ノルウェイの森』を読んだ時の感想と、三十代になって読んだ時の感想とは全く異なっている。高校生の時は、その性描写が過激に写ったし、そもそも主人公の学生があまりにノンポリにすぎるように思えた。今でもあまり変わりはないが、その頃は今以上に痛烈にノンポリを害悪だと思っていたから、作品自体に対する評価も否定的だった。ところが、三十代で改めて読み直してみると、高校生の自分にはノンポリに見えたその主人公が、実はノンポリの正反対、すなわち狭い意味でポリティカルであるわけではないが主人公なりに世界の問題を意識し鋭く批判しているということが行間から読めたのである。そもそも、この体験が、村上春樹の全著作を読破してみようと思った発端だった気がする。それゆえ、昨今東アジア地域で村上作品が読まれる際の、スタイリッシュな都会派生活とその孤独感などという読みは、裾野を広げる意味はあっても、どうも真の作品理解とは言えないような気がして仕方ない。
少し脱線したが、つまり、言いたいのは、読後直後の感想は得てして変わりうる、ということである。読了から今に至る、たった数日の間ですら、感じ方は刻々と変化してきている。ましてや、『1Q84』読本なるものまで登場しているのだから、そんなものをパラパラめくった日には、ぐらぐらと自分の中の印象が揺さぶられて、その他大勢の感想の中に埋もれて雲散霧消してしまうかもしれないし、ある批評の影響を受けてそれに同調してしまうかもしれない。しかし、いや、だからこそ、読後直後のナマな自分の感想をメモしておきたいと思う。できれば一刻も早く。
以下、極私的覚え書き。
・ 初めのうちは良かった。第1巻は、言葉は悪いが、まるで新聞の三面記事を読むような感覚で「なになに、次は一体どうなるんだ??」という調子で、ぐいぐいとストーリー展開に引き込まれた。細部もいいし、全体のバランスもいい。並行して進められる二つのお話において、あらゆる事柄が一定のリズムでめくるめく語られ、「この本で村上春樹は世界を描ききってしまうのではないか」という、かなり大げさに言えば、怖れみたいなものすら抱いた。
・ 作風、テイストについても、第1巻においてはブレはなかったと思う。つまり、作者は物語を制御しきれている、あるいは、誰か理性を持った者によって物語が管理されている、という感じがあった。つまり、たとえば『ねじまき鳥クロニクル』では、夫婦の話がそのうちにノモンハン事件へと一気に飛躍してしまう感じがあって、途中から何度もテイストが変わっていくのだが、今回はそうした作品の雰囲気、テイストは少なくとも前半においては変わることなく、がっしりと構築されているように思えた。とはいえ、これは良いことなのか、悪いことなのか。テイストの変化は、作品の完成度を左右するか。少なくとも『ねじまき鳥』を読んでいる最中は、そうしたテイストの変化が必然のように感じられたし、そうした言わば不器用なゴツゴツとしたものが作家という通り道をくぐり抜け提示された生まれたての物語なのであり、それこそ「ものがたり」なのだと思える高まりがあった。だからこそ、解決されないナゾが残ろうと、そこには強い魅力があった。しかし、そうした魅力とは異なった、ぶれない魅力というものが、もしかしてこの新しい作品にはあるのかもしれない、と期待した。
・ 本書には、冒頭から暗い部分があり、暴力性と言っていいかもしれない面が織りこまれている。それらの背景として、『アフターダーク』における闇の延長が感じられた。たしか、誰もいない暗い部屋の中に箱が置いてあるような、そういうシーンが何回か描かれていたように思う。このシーンが持っている闇、うす気味悪さ、暴力は、本作品においてどのような着地点を見出すのか、という興味もあった。
・ 第1巻の終わる頃、二つの並行して進むお話に、ある接点が示唆され始めると、がぜん面白くなって、期待が高まる。しかし、第2巻に入り、はっきりと両者が接続されてくると、話のスケールが一気にしぼんで、単なる男女二人の出会いものになってしまった。
・ この本の出版翌日の朝のNHKニュースで、某という評論家が登場し、「本書は言わば、村上春樹のオウム取材の経験から生み出された小説である」という内容のことを話しているのを見た。村上春樹によるオウム取材の結実としては、地下鉄サリン事件被害者やオウム信者へのインタビュー集である『アンダーグラウンド』と『約束された場所で』がけっこう良かったので、その番組を見て以降、「小説ではオウムという要素は果たしてどうなるのか」、「小説の中で宗教はどのよう描かれるのか」というのが今回自分のこの本に対する最大の関心事となった。しかし、それはこちらの勝手な思い込みだったのかもしれない。つまり、どういうことかと言うと、もしかしてこの作品の中で宗教は自分が期待したほど重要な扱いを受けていないのかもしれない、ということである。というのも、この物語で描かれる宗教とは言ってみればカルト宗教であるが、単に教祖が超能力を持っているということが描かれるのみなのである。超能力を見せられて、これが宗教です、信者を集めてますと言われても、説得力がない、と思う。もちろん、新約聖書を読めば、イエス・キリストだって数々の奇跡を行なったことが知られる。しかし、イエスの奇跡は人を救う奇跡だった、と思う。やみくもにベッドサイドの置き時計を念力で持ち上げたりはしないし、千里眼のように人の心理を見通して言い当てたりもしない。それって、あまりにプリミティブにすぎる。それにまた、そうした教祖を信じる信者たちの信仰の諸相については描写がない。触れずにベールに包むことにより、不気味さを醸し出そうとしているのだと思うけれど、そのせいで、そうした教団が存在するということのリアリティーも今ひとつ湧いてこない。
・ 主人公の男性と、カルト教団の巫女的存在である少女とのセックスが描かれるが、どうも、このセックスを宗教的行為、秘儀のように捉えているフシがあって、この単純さは頂けない。『海辺のカフカ』で、主人公の少年と、想像上の母親が近親相姦する描写があるが、それ以上に単純というか、薄っぺらである。本作に限らないが、春樹作品はセックスに物語の重要な要素を預けすぎるきらいがある。
・ 物語の最後は、結局、三十歳前後の男の自立物語に終わる。これじゃあ、結果は『ダンス・ダンス・ダンス』と同じだ。主人公に共感できることを望むわけではないが、四十間近の読者として見れば、今さら三十男の父親からの自立なるものに付き合わされることほどつまらないことはない。そもそも春樹はなぜいつも若者ばかりを主人公とするのか。なぜ、六十代の人間が、若者ばかりを描くのか。中年や老年を描けないのか。まさか、読者層(購買層)をマーケティングした結果ではないと思うのだけれど。たとえば、春樹が全訳しているレイモンド・カーヴァーだって、ほとんど主人公は中年男性だし、春樹自身もエッセイでは『遠い太鼓』で四十という大台にのぼる境い目の心の動きを如実に記している。また『グレート・ギャッツビー』の訳者あとがきでは、六十に差しかかった作家の切実な焦りが記されてもいる。だから、なぜだろうと思う。
今は、そのうちまた読み直す機会がやって来て、この読後感を大きく変えてくれることを、期待しています。
『1Q84』読み始め [村上春樹]
いやー戻ってくるまで長かったなぁ。
ということで、ちまたを席巻している『1Q84』をついに購入した。なんでも現在、東京の印刷所・製本所は、この本の嵐が吹き荒れており、大わらわであるとの由。
ベストセラーにはつい斜に構えてしまい、これまで流行っている最中に買ったことは、あまりない。『ダヴィンチ・コード』を読んだのは翻訳が出てから3年後だし、『超整理法』に至っては出版後10年以上経った昨年初めて読んだ。いずれもたいへん面白く読んだ。しかし、周りに話そうにも、皆、忘却の彼方である。やはり面白い本については、流行っているうちに読んで、皆と感想を共有したいもんだなぁと思ったりする。それに、そもそも村上春樹の新作に対して斜に構えると、何のために同時代作家を選んで読破してやろうと決めたか分からなくなる。といった理由で、今、嵐が吹き荒れているうちに読んでみようと思ったのである。
現在、読んだのは上下全48章のうち、9章まで。約5分の1。紙の厚さにしておよそ8ミリ程度である。しかして、ほとんど読まずに語る状態ではあるが、今の時点で、自分の期待も含めて、いくつかメモを取っておきたい。
・ 『世界と終わりとハードボイルド・ワンダーランド』において、「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」に分けて物語が同時進行したのと同様に、また、たしか『海辺のカフカ』とも同様に、本作においても二つの物語が同時進行する。このような方式が幾度も採られるということには、村上作品を分析する上でどういう意味があるのだろうか。あるいは、どの作家もやっている常套の手段として片付けていいものだろうか。
・ 主人公の一人は小説家の卵であり、この人物が文章を作っていく過程が克明に書かれている点は、個人的に非常に興味深い。なぜならそれが、普段自分が仕事で作文している作業過程によく似ていて、とてもよく分かったからだ。これまで、小説家というのは、自分の中から沸き上がる物語を自然に紙に書き留めていくような印象を持っていたが、実は違って、自分が作文する時と同じように、とりあえず打ち込んだ上で、それを何遍も推敲する、ということをするんであるなぁと思った。推敲、と一言でいうけれど、すなわちその過程とは、ひとまず題材とすべき事柄を羅列すること、その中で重要なポイントを抽出すること、それに相応しい言葉を選ぶこと、こなれた言葉を選ぶこと、そして最終的には自分というナマの状態を出さず、文章のみで事柄を伝えるようにすること。こうしたことが、明確に書かれていて、意を得た感じを抱いた。
・ 村上春樹は、『ノルウェイの森』において、リアリズム小説にチャレンジした、と語っている(出典はたしか『そうだ村上さんに聞いてみよう』とか何とかいう本だったと思う)。したがって、つまりはそれ以前の作品においては、ファンタジーというか、超常現象というか、とにかく空想的な事象(典型的には羊男という存在など)が描かれていて、それが春樹の作品の独特な雰囲気を醸し出しているのである。ということを踏まえると、本作においてオウム真理教取材の経験によって新興宗教を取り上げると聞けば、おそらく彼らの反社会性を批判するのであろうと推測してしまうのだけれど、考えてみれば、新興宗教あるいは都会派宗教のもつオカルティックな部分については、村上作品はファンタジーという表現において類似性を有しているのではないだろうか。つまり作風的には何ら新規で突飛な分野ではなかろうというふうに思う。(しかしすぐに注記しておくが、これは決して、春樹がオウムにシンパシーを抱いているということを言っているのではない。職場で話したら、そのように誤解された)。
・ 本作において宗教が描かれるのであれば、それがどのようなものであるかはまだ分からないが(何せ読み始めたばかりゆえ)、大江健三郎が『燃え上がる緑の木』で描いたような宗教的な物語を描けるかどうか、というのが個人的に注目したい点である。なぜなら、村上は『海辺のカフカ』で大江的な四国を舞台とした物語を書いているし、何かにつけ大江とは因縁の仲であろうはずだからということもある。が、それ以上に、あくまで個人的な問題意識として、この無宗教の日本という地において、日本語で、果たしてどのような宗教的物語が生み出され、受け入れられるか、ということに関心があるのである。これは個人的な、半ば期待である。もちろん、オウム真理教の反社会性、すなわちそれはこれまで村上作品で取り上げられてきた、旧日本軍や全共闘運動にも共通する日本の問題性でもあるのであるが、そうした日本に巣くう無責任構造、事なかれ主義、日和見主義等々を取り上げて、奥底で辛辣な批判を加えるのは大歓迎なのではあるけれど、ここでは一つ、宗教物語、というものを期待しておきたい。
そういうことで、読むのが楽しみです。
春樹情報、覚え書の巻。 [村上春樹]
イルカくんです、こんにちは。
夏本番、8月になりましたね。皆さま、夏休みはどのように過ごされますか? イルカくんは明後日から夏休みを戴きます。それで、ほんの少しブログの世界とも離れますので、今後に向けて個人的にいくつか気になってる春樹情報をメモしておきたいと思います。
1)しばらく前に書いた「村上春樹と中国」ですが、そこで全面的に参考にさせていただいた小論文の著者、藤井省三先生が、今度は朝日新聞社の『一冊の本』8月号に「村上春樹と魯迅および東アジア」と題する一文をお書きでした。本屋で無料でゲットしてきましたとも。はい。同誌9月号から新連載「中国のなかの村上春樹」が始まるとのこと、要チェックです!
2)イルカくんの失態、じつは村上春樹のホームページ「村上朝日堂」がついこの間まで、期間限定で復活していた……。し、し、知らなかった。1999年11月に無期限更新中止になっていた同ホームページは、『これだけは、村上さんに言っておこう』(2006年、朝日新聞社)の発売に合わせて、3月8日から3ヶ月間だけ開設されていたそうです。イルカくんはこの前たまたま知りました。その三ヶ月間は、村上さんにメイルも送れて、もしかしたら返事も貰えたかもしれないんです。このブログを始めたのが5月23日ですから、ちょうどその頃ですよ。本当に不覚だったなあと、ただただ嘆いております。
3)まあ、しょうがないか、と気を取り直して。それで「村上朝日堂」で知った新事実。春樹氏は5月1日現在のところ、フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』とレイモンド・チャンドラーの『ロング・グッドバイ』(既訳では『長いお別れ』)を翻訳中とのこと!! これって、スゴくないですか。イルカくんはけっこう楽しみです。『ギャツビー』は今年の年末ごろ中央公論新社より、チャンドラーのほうは早川書房から来年の春ごろに出版できそうだと書いてありました。『ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック』では、あとがき(1988年)の最後に、「六十を過ぎた頃には、あるいは『グレート・ギャツビー』を訳せるようになっているかもしれない」とあるから、満を持してという感じだと思います。
4)えっと、「村上春樹と中国」の回でも書きましたが、じつは『村上春樹全作品』というのが気になっています。藤井先生の論文でも書かれていた通り、短篇については『全作品』収録の際に書き直されているものがあるのと、それから作者本人による作品解説が付いているらしいのとで、イルカくんは是非ともチェックせねばと思っていたわけです。そんな時、仕事で立ち寄った図書館で見つけたんですけれど、なんと第1期については村上自身による「自作を語る」が月報のかたちになっていて、そこの図書館では月報だけをまとめて綴じて貸し出していました。もちろん借りて、今ちょこちょこ読んでいます。第2期については、月報ではなく、本の中に自作解説が収録されているようなので、これはやはり重い本を借りなくてはなりません。そのうちに近所の図書館に行ってみるつもりです。
そんな感じで、個人的な覚え書きでした。どうぞ、皆さんも、よい夏休みを! チャオ。
村上春樹訳『キャッチャー』雑感。 [村上春樹]
イルカくんです、こんにちは。
村上訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(白水社)が出たのは2003年の話ですけれど、村上春樹の初期作から読み始めてようやくここまで辿り着いてみると、「とうとう春樹は『キャッチャー』を訳しちゃったか……」という感慨がないでもないです。というのも、たしか、初期のエッセイや短篇なんかで『キャッチャー』の主人公ホールデンの名前が出てきていたから。イルカくんは学生時代に原文で『キャッチャー』を読んで、けっこうホールデンには親近感があったので、村上訳には期待するところがありました。さて、その結果は……。
本当に悲しいことに、正直いうと今回は、ホールデン・コールフィールドに入りきれませんでした。それは何故なんだろうか? 考えられる理由、1)春樹の訳が悪かった(宿命的な翻訳不可能性)。あるいは、2)イルカくんがインチキな大人になっちまった。う〜む、どっちでしょう?
1)翻訳の問題でいうと、個人的には、昔から出ている野崎孝訳よりは村上訳の方が格段に良いと思います。この小説は口語的に書かれていて、俗語(1950年代の)もたくさん入っているので、日本語訳も当然口語調になるのは定めだと思うんですが、野崎訳は年代物なので話し言葉の感覚が今とズレています。大昔ちょっとだけ立ち読みしましたが、最初の一文でもう鳥肌が立ったことを覚えています。まあ、その時はイルカくんも上京したてで、東京の話し言葉にぜんぜん慣れてなかったということも大きいと思うので、今読んだらもしかしてスラスラ読み進められるのかもしれませんけれど。
一方、春樹の訳に対しては拒絶反応もなく、安心してすんなりと入れました。ただ、当然というべきか、訳には若干の春樹テイストもあって、たとえばホールデンが「やれやれ」とか言っちゃうと、それはなんか違うんではないかと思うわけです。これはまあ些細なことではあるんですけれど、そういう細部の作りって、小説世界ではけっこう大切じゃないですか。でも、自分の中で村上訳以外の『キャッチャー』イメージがなければ、村上訳はぜんぜんオッケーなんだと思います。むしろ、村上訳で初めて『キャッチャー』に触れる人がいたら、それはけっこう幸せなことだと思います。要するに、イルカくんの違和感の問題は単純に、前に読んでいたということが大きいのかもしれません。
2)では次に、時間の経過の問題。今回、村上訳を読むまでは、『キャッチャー』の内容の詳細は、ほとんど忘れていました。覚えていたことは、ホールデンは変化したくないと思っている、変化しない世界を求めているということで、その点がイルカくんとホールデンとの繋がりだったわけです。具体的には、弟アリーのお墓のこと、小学校の壁に「ファック・ユー」という落書きがあったこと、そんな言葉を妹たちに知られてはいけないとホールデンが思っていること、そして博物館のミイラのこと。それ以外はぜんぜん覚えていなかった。
それで新しく春樹版を読むと、上の記憶以外の箇所については、なんだか、「そんな小さいことでいちいちクヨクヨするなよ」とかホールデンに対し思ってしまったんです。「世の中、そんなことなんか脇に押しやるくらいに飛んでもないこと沢山あるよ」とか思っちゃったんです。それで、過去にたしかに自分のものとしてあった、ホールデンとの繋がりがシュ〜ンとしぼんでしまった気がしました。もし自分がアントリーニ先生だったら、ホールデンになんて話すだろうなんて考える始末。ちょっと寂しい読後感でした。ああ、ホールデンとの個人的な繋がりは、本当に永遠に失われてしまったのか……。
村上春樹は翻訳刊行後、『翻訳夜話2 サリンジャー戦記』(共著、文春文庫、2003年)を出して、その中で、『キャッチャー』に対する自分の見方を語っています。一つ、彼の主張は、『キャッチャー』は60年代に若者のバイブルとなったが、この小説はけっして若者の反抗の話ではない、ということ。ホールデンはやみくもにエスタブリッシュに反抗しているわけではない、これは事実。村上の言うとおり、これはホールデンの自己の探究の物語です。言葉を借りれば「本当はこの小説の中心的な意味あいは、ホールデン・コールフィールドという一人の男の子の内的葛藤というか、『自己存在をどこにもっていくか』という個人的闘いぶりにあったんじゃなかったのか」ということです。つまり、この本は別に若者に限定された本じゃない。だから、イルカくんも、また時間をおいて読み返してみようと思います。そうすれば、今よりは素直に読めるかもしれない、そんな希望を抱いています。どうかな。
ちなみに『サリンジャー戦記』には、訳書に契約上掲載できなかった、春樹による訳者解説も収録されています。
村上春樹と中国(その3) [村上春樹]
イルカくんです、こんにちは。
結局、春樹にとって中国とはどういう存在なのか。
藤井省三「村上春樹のなかの中国を読む」第3回(『UP』7月号)は、「「ジェイズ・バー」という歴史の記憶−−『風の歌を聴け』論」という題で、『風の歌を聴け』『一九七三年のピンボール』『羊をめぐる冒険』に登場する「ジェイズ・バー」のマスター、「ジェイ」とは何者かという謎解きから始まります。
曰く、「ジェイとはアメリカ兵により命名されて中国名を失った在日中国人」であり、「戦後の日中米三国間系の目撃者」である、と。そして、「僕」が日本軍兵士として上海で死んだ叔父の話を「ジェイ」に語っていることなどから、「ジェイズ・バー」とはすなわち、「日中戦争から朝鮮戦争、ベトナム戦争という二〇世紀の半ばに東アジアで日中米の三ヵ国が入り乱れて戦った戦争体験を記憶する場であったのだ」と。
藤井論文はこのように「ジェイ」と「ジェイズ・バー」を位置づけてから、その延長として、のちの『ねじまき鳥クロニクル』および最近の『アフターダーク』における歴史の描かれ方についても独自の読解をして、そうした上で1998年に台湾誌のインタビューに答えた村上自身の言葉を紹介しています。このインタビューが、なんというか、イルカくんにとってはけっこうな大発見だったんですけれど、村上春樹という小説家の創作の秘密を知る上でかなり重要な話なんだと思います。引用します。
「僕の父は戦争中に徴兵されて中国大陸に行きました。父は大学時代に徴兵されて兵隊となったのでして、父の人生はあの戦争のために大きく変わってしまいました。僕が子供の頃の父は決して戦争のことは口にしませんでしたが、しばしば中国の風土や民情を話していました。「中国」は僕にとって実在するものではありませんが、しかしとても大事な「記号」なのです。……僕はただ僕の記憶の影を書いているだけなのです。中国は僕にとって書こうと思って苦心して想像するものではなく、「中国」は僕の人生における重要な「記号」なのです。」(44頁。原記事は洪金珠「村上春樹的霊魂裏住着中国記印」『中国時報』1998年8月5日)
えっと、これまでイルカくんは、春樹作品にみる日中関係の歴史というテーマも「全共闘世代と村上春樹」という視点から考えることができるんじゃないか、言い換えると、春樹が日中戦争に関心をもつのは彼の過ごした学生運動という時代の関心が反映しているのではないか、なんて思っていたんですけれど、このインタビューによってその仮説をくつがえされました。なんだか、そんな浅薄な推測をした自分が恥ずかしくなっちまいます。つまり、春樹にとっての「中国」とは、学生時代のいわば後天的な記憶ではなく、子供時代の、言ってみれば先天的な記憶によって成立しているのです。中国というテーマは春樹にとって、とても個人的なものなんだ、と考えることによって初めて、初期作品から現在まで一貫して扱われてきたことの説明がつくんだと思います。
藤井氏はまた、朝日新聞でのインタビューも引用していて、それによると春樹は次のように答えているそうです。「僕にとって、日中戦争というか、東アジアにおいて日本が展開した戦争というのは、ひとつのテーマになっています。」(44頁。原記事は由里幸子「村上春樹が語る(下)揺れ動く世界と若者と」『朝日新聞』2005年10月4日夕刊)
ここまで明確に答えているのは、意外な印象もありますけれど、それゆえにスゴイことだと思います。これで、村上春樹の軟派イメージって一掃されるんじゃないでしょうか。イルカくんは、春樹の軟派エッセイ(?)も好きなんですけれど、それはそれとして……。
藤井論文は最後に、「これまで記号としての「中国」を書いてきた村上春樹は、いよいよ東アジアの歴史の記憶を直視する作品を書き始めているのではあるまいか」との推論で締めくくられます。これって、けっこう面白い推測ですよね。春樹は『アンダーグラウンド』でサリン事件の取材をして、その頃から、いずれは暴力について書いてみたいと言ってますし、次の作品のテーマとしていったいどんなものが選ばれるのか、そういう楽しみ方も有りだと思います。
これで一応「村上春樹と中国」はおしまいですけれど、藤井先生のご論文にぐぐっと刺激を受けて、イルカくんの今後の読書計画としては、『村上春樹全作品』をどこかでゲットすることと、早く『アフターダーク』までたどり着くこと、そして『ねじまき鳥』を読み返すことかな。今は、じつは『翻訳夜話2サリンジャー戦記』(共著、2003年、文春文庫)を読んでいまして、これがまたなかなか面白いので、また近いうちに、村上訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の話とともに書きたいと思っています。